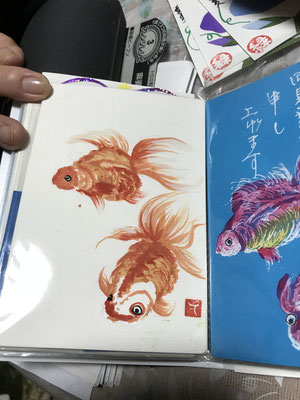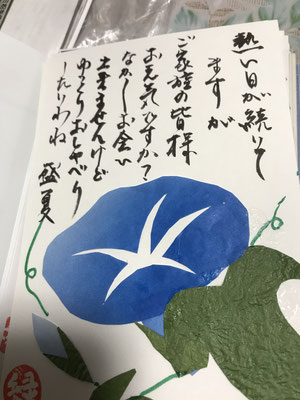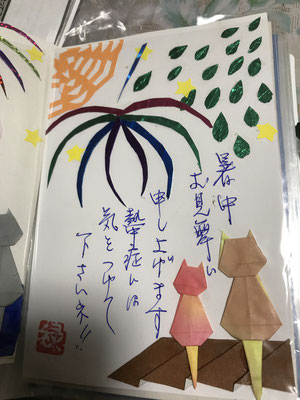R7年4月の俳句:短歌:川柳 投稿壇
◎総評:今月から兼題句を設ける事になりました。
題を設けての俳句は難しく俳句の中級過程的な勉強でもあります。
また、本来ならひとつの語を設けますが、歳時記を広げる機会もより多くなり、
季語の本来の意味を解するのにも絶好かと思い題名に「季語」を用いてみました。
その途端、結構な兼題句を賜り吃驚しています。
偏に皆様の熱心さの表れと、嬉しい悲鳴をあげて鑑賞致します。
※「俳句するに際しては先ず歳時記を捲って(めくって)この句に使用した季語の否諾を
考えてみましょう。句に対して妥当である季語が大切なのです。歳時記を読み返しましょう」。
●文芸編集部より
寸評:推敲:選者=片桐基城先生
※複数の句の投稿者の方へ:寸評、添削は一人一句をして居りますのでご了承お願い致します。
(先生は投稿句全句を推敲成され、その中で佳句を一人一句として挙げて居ります。)
紙面の都合上、選外の作品は掲載致しませんので御了承の程宜しくお願い致します。
●今月の選外作品句は4句でした。
☆優秀句を一席~三席との表記を「天・地・人」としました。
他の表記は「◎」次点、「〇」次々点。
【毎月の投稿〆切日=10日】
☆俳句の部
〔金子敏枝:江二〕
天:「岩山に色を添えたる山桜」
・寸評:岩が競う山肌を染める桜の花を詠った、その発見に拍手します。
が、この焉体系「たる」でも良いのですが、思い切って「いる」と終止形で
表現したら如何でしょう。
※下記の「地」・「人」と推した二句に優劣を付け難いので、全てが(地)位句と言っては
大袈裟ですが、そう思ってお読みください。
〔青木幸子:事務局職員〕
地:「桜雨無色の都会染めてゆく」
・寸評:色彩感の無い都会を染める雨、言葉の配列を変えて。
・添削:「色気無き都会を染める花の雨」
〔渡邉孝之:江二〕
人:「里桜木肌に老いを感じみる」
・寸評:どっしりと太く育った桜の樹に感じた老い。
・添削:「樹の肌に老いを感じる里桜」
〔角田和道:今光一〕
◎「思い出の夢を語りし老桜」
・寸評:あれこれと頷ける素敵な句です。唯、夢を思いでに限定しないで「幾つもの」
ではどうでしょう。また、「中七」「語りし」と止めないで、「語れる」と
連用形で繋ぎたいですね。
・添削:「幾つもの夢を語れる老桜」
〔金子敏枝:江二〕
○「休耕の畔一面にいぬふぐり」
・寸評:瑠璃色に咲く綺麗ないぬふぐりの花が、休田の畦道を染める様に咲いている
様子が、目の前に移って見えてくる素敵な句です。極く普通に詠いながらに
深い詩生があります。
〔渡邉孝之:江二〕
●「飛び花や破風を伝いてひらはらり」
・寸評:破風、つまり屋根の切妻を伝って散る花を詠っているのですね。
上五の「飛び花」は図り事を云う言葉ですので。
・添削:「桜いま破風を伝いて飛花落花」
〔金子龍夫:江二〕
・「古里の紅梅白梅香我想う」
・寸評:その名の梅人形もありますが、俳句は一人称は既存していますので省略
しましょう。
〔石岡ノブ:高根沢〕
・「千代紙を散り放せたる花筏」
・寸評:花筏の様子が見えてきますが、「千切ったような」と、あっさり擬人化したいですね。
・ 添削:「千代紙を千切ったような花筏」
〔角田則子:今光一〕
・「おさなき日わが学び舎に桜舞う」
・寸評:春の思い出の詠ですね。文字を省いて・・・。
・添削:「花の舞う学び舎に来て背伸びする」
〔金子龍夫:江二〕
・「桜散るお堀の水面ピンク染め」
・寸評:極端な言い方をするようで失礼ですが、花が散った後の花筏の説明に終わっています。
〔林 弘:壬生二〕
・「メール来しあの子に桜咲きました」
・寸評:メル友に、花が咲いたと返信ですね。詩心を入れ。
・添削:「思い出の地に花咲くと返信す」
〔安保 孝:江二〕
・「水屋にて身ぶるい一回春近し」
・寸評:茶碗や皿等を収納する茶箪笥を前に、寒さを感じて身震いに春を感じたのですね。
〔清澤 修:壬生一〕
・「揚げ雲雀声高らかにラブソング」
・寸評:雲雀の可愛く情的に鳴く声を「ラブソング」と捉えて素敵です。
あと一つ欲しい句。
〔鈴木サト子:石宮〕
・「庭さきのかわいく咲いた花一りん」
・寸評:この、可愛い花は何の花でしょう。「花」と言えば「桜」です。
〔大和佳子:松原〕
・「春一番やって来たのはスギ花粉」
・寸評:立春後の南風と共にスギ花粉に見舞われたのですね。
二つある季語を削りましょう。※(季重り)「春一番」・「スギ花粉」
☆短歌の部
〔福田時子:江曽島教区二部〕
・「日本晴れ桜満開門くぐり母親一人じめ昔懐かし」
・寸評:何か所も言葉を切っているので、強調したい事を絞ってみませんか。
「日本晴れ」も読みての想像に任せ。
・添削:「母親を独り占めして満開の花観るあの日そぞろ懐かし」
〔植木誠一:西原〕
・「満開の桜見る度思い出す八幡山への家族旅行」
・寸評:このままで完成されていますが、中七「桜見る度」の桜を花として一字を省略し、
また助詞を入れて「花を観る度」ですっきりします。家族の旅行は忘れ難いですね。
〔植木誠一:西原〕
・「桜より常に輝く常照寺皆が引き継ぐ大師の教え」
・寸評:固有名詞は避けたいですが敢えて避けず、また、思い切って後と前を入れ替え、
①「経文の教えを皆で継いでいる」②「花のように輝いている・・・」と、滑らかに
詠っては。
※編集後記:細心の注意を払って誤植、脱字、書き違いが無いように編集して居りますが
もしそのような事が有りましたらお許しください。又、文芸編集部までお知らせ下さい。
ご信者皆様の投稿 、奮ってご参加ご披露をお待ち申し上げます。 【毎月投稿〆切日=10日】
投稿ご希望の方は事務所へ提出、若しくは宇清師、陽哲師、渡邉孝之までお申し込みください。
投稿フォームでも受付しております。
受付次第ホームページに掲載させて頂きます。
バックナンバー
俳句・短歌・詩・小説・マンガなど。あれもこれもご披露ください。
新着情報
〇YouTube公開
「いっしょにお看経してみませんか?」
本堂で一緒にお看経しているような気分になれる30分ほどの動画です。
みなさんも一緒にお看経してみませんか?

〇「常に照らさん常照寺」 YouTube公開
先住・井上日宇御導師が作詞をされました
「常に照らさん常照寺」をYouTubeで公開しました。

〇本堂の左前、お塔婆の前に線香台を設けました。お塔婆を建立された方は、ぜひ、本堂でもお線香をあげてください。
本門佛立宗 常照寺
〒320-0806 栃木県宇都宮市中央3-11-13
TEL : 028-634-4205
FAX : 028-637-9207
Copyright © 2021 Honmon Butsuryu-Shu Joushouji Inc. All Rights Reserved.